 マンションの購入
マンションの購入 築30年を超えるマンションの未来:購入時に考慮すべき点とは?
築30年を超えるマンション購入時のポイントを徹底解説。耐用年数、価格の魅力、リニューアルのタイミング、新耐震基準の安心感、そして大規模修繕の実績について、将来的な居住計画や資産価値を見据えた有益な情報を提供します。築30年物件の選択に際して、管理状態や改修費用の観点からも総合的なアドバイスを行い、後悔しない物件選びをサポートします。
 マンションの購入
マンションの購入  マンションの購入
マンションの購入  マンションの購入
マンションの購入 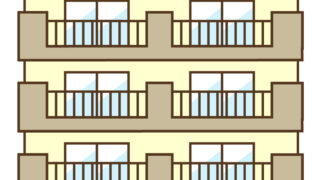 マンションの購入
マンションの購入 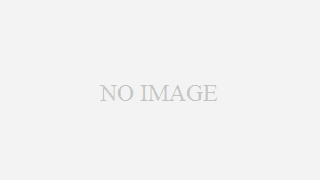 マンションの購入
マンションの購入 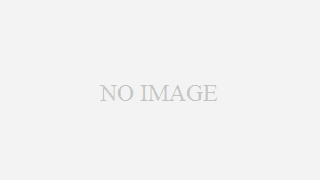 マンションの購入
マンションの購入 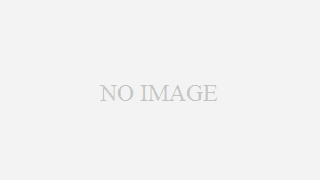 マンションの購入
マンションの購入  マンションの購入
マンションの購入